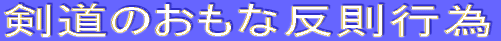1. 「.竹刀をおとす」
どんな理由であれ竹刀を落とした人は反則とされます。
2. 「竹刀の刃部をつかむ」
自分の竹刀でも、相手の竹刀でも試合時間中に竹刀の刃部をつかんだら反則です。
3. 「試合場外にでる」
試合中、体の一部(足、手、お尻など)が出たら反則とされます。
体勢上、外に出ないと試合ができない状態になった場合などは反則に
ならなかったりと、けっこうケース・バイ・ケースですね。
4.. 「相手を不当に場外に出す]
上記の3. とは逆のパターン相撲ではないので無理やり出したら反則です。
5. 「相手に足を掛け または払う 」
柔道ではないので反則です。
6. 「不当なつば競り合い および打突をする」
つば競り合い反則はかなりメジャーな反則ですね。気をつけましょう。
打突に結び付かない危険な行為はもちもん反則。
7. 「相手に手をかけ または抱え込む」
竹刀を落とした選手が咄嗟にやる抱えこみ(笑)
その場合 二重の反則となりますが、先の反則(竹刀落し)だけカウントされるようです。
実は私も試合中相手に抱え込まれたことがありますが、「口頭で注意」ですんでました。
8. 「相手の竹刀を抱える」
9. 「相手の肩にわざと竹刀をかける」
これって不当なつば競り合いに入るのでは???
わざと、とか故意にって見極め難しいです。
10. 「倒れたときに 相手の攻撃に対応する事なく うつ伏せなどになる」
11. 「わざと時間の空費をする」
勝ち逃げ、引き分け狙いでの行動ですね。いけません。
12. 「防具が頻繁にはずれる」
試合中に何らかの理由で防具がはずれる場合がありますがそれは反則になりません。
ただし、安全に対する注意義務を著しく怠り、これによって試合を継続することが
不可能になる重大なミスであれば反則。
頻繁にはずれるのも反則。
以上がほとんどの反則行為となります。
それと反則以上の行為がありますので、下に記しておきます。
1. 「一本決まったあとのガッツポーズ 」
これをやると、見苦しい引き上げとして「一本取り消し」処分になります。
「人を斬っておいて喜ぶとは何事だ。」という意味もあるのでしょう。
(でも柔道の選手ってこれやるんですよねえ、、、)
私は過去中学生の試合で2回ほど「取り消し処分」を見たことがあります。
2. 「相手や審判に対する非礼な言動」
これをやるとそれまでにとった本数、既得権全て剥奪され、相手に2本
あたえ即刻退場を命じられます。場合によっては今後その大会には
出られないでしょう。さすがにここまでやった人は見た事ありませんが、、、
3. 「薬物を使用する」
これも上記と同じく相手に2本あたえ即刻退場です。
しかし剣道にはドーピング検査などなく、また薬物が何を指すかは
いまだ未定のようです。まあ「麻薬」などは論外ですが、「風邪薬」「アレルギー
を抑える薬」などは???どうなるのでしょう???
4. 「定められた以外の用具を使用する」
最近では異様に軽い「不正竹刀」が高校生のあいだで問題になっているようです。
剣先を軽くして柄の中に規定重量に足りない分重りを入れたり、
検量逃れしてみたり、、、見つかったら相手に2本与えて試合終了となり
その後の試合は出られませんが退場処分とまではいかず補欠による代理選手は認められます。
それ以外にも5本指籠手なんてのも認められません。
なぎなた用の防具も使えません。
以上、反則行為は反則なので(?)試合に出る人は早くおぼえてしまいましょう。

1.剣道の試合場は9〜11mの長方形の枠線の中で行います。
2.試合時間はその大会の規模、学年によってマチマチのようです。
大会の開会式に説明があるので必ずきいてください。
ちなみに当クラブでは小学1年〜小3までは1分30秒
小4は2分、小5、小6は2分30秒、中学生は3分、
高校生以上は4分となっています。
主審が有効打突や試合の中断を宣告し、そのあと試合再開までに
要した時間は試合時間に含まれません。
3.試合時間内に先に相手から2本とったほうが勝者となります。
(これを3本勝負といいます)
ただし2本とれなくても、一方が一本をとりそのまま時間が終われば
そのほうが勝者(一本勝ち)となります。
また、試合開始時間になっても相手が現れない場合も勝ち(不戦勝)
となります。とくに団体戦においては二本勝ち扱いとされます。
4.時間内に勝負が決まらなければ、延長戦になります。
延長戦は基本的に時間無制限の一本勝負です。
(当クラブでは小学生低学年は延長戦は1分で2回まで行い
それでも勝負が決しない場合は判定になります)
ただし、団体戦などは延長戦をやらずに引き分けとする場合もあります。
5.審判は主審1名 副審2名の3審制で行います。
有効打突の判定は3名の多数決で決まります。
つまり二人以上が一本と判定しなければ一本になりません。
ただし反則のジャッジは審判全員一致が基本のようです。
意見が分かれた場合は合議をかけ意見調整します。
6.一本、つまり有効打突は「気・剣・体の一致」「正しい刃筋」
「竹刀の打突部で、打突部位を打突」「「充実した気勢」「適法な姿勢」
「打った後の残心」を各審判員が総合的に判断します。
「これをしたから1点」というスポーツと、武道のちがいはこういった
ところにあるのかもしれませんね。
7.有効打突ではないが一本とられる場合があります。
それは反則を2回やってしまった場合です。反則を2回やってしまった人は
相手に一本をあたえ、自分の反則カウントはリセットされます。
8.竹刀の長さは小学生36(3尺6寸、111cm)以下、中学生37以下、
高校生38以下、一般は39(120cm)以下とさだめられています。
(厳密には重さや太さも男女別に細かく規定があります。)
竹刀の打突部(物打ち)とは、竹刀の剣先から中結いまで(切先3寸という)
の、刃側をいいます。
9.打突部位とは面部(正面、右面、左面)、小手部(右小手、条件により左小手)
胴部(右胴、左胴)、突部(高校生以上、胸突きは廃止)をいいます。